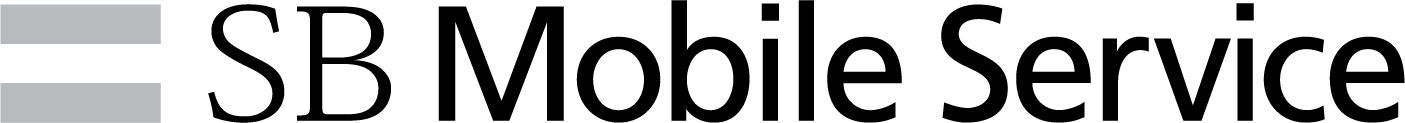RPAとは?
働き方改革の促進、そして2020年の新型コロナウイルスの影響により、業務のIT化は今後さらに拡大していくと考えられます。
このような情勢で、RPAは今後も急速な伸びが予測されているサービスです。
RPAツールを使えばプログラミング経験がなくてもシナリオ作成ができるという手軽さから、導入する企業も増えてきています。
本ページでは昨今急速に普及してきているRPAの概要を簡単にご紹介します。
リモートワークの加速とともに、さらにRPAで業務を自動化させる動きが注目されております。


RPAとは
RPAとは「Robotic Process Automation」(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略称で、簡単に言うと「これまで人間が行ってきた定型的な業務をソフトウエアのロボットにより自動化する」概念のことです。
主にホワイトカラーのバックオフィス作業をルールエンジンやAI(人工知能)などの技術を備えたソフトウェアのロボットが代行することで、業務の自動化・効率化が可能となります。
RPAツールは、人が手入力で行ってきたパソコンの事務作業をソフトウェアロボットで自動化するなど、昨今の企業の変革に欠かせないツールとして注目されております。
たとえば、メールに添付されてきた商品情報をまとめたExcelファイルの内容を、社内で使用する商品登録システムにコピーやペーストして行う登録作業や、FAXで届いた発注書の内容を手入力でシステムに登録する作業、手動でフォルダに格納する作業や、目検で行っている提出書類の不備チェックなど これらの定型的で反復性の高い業務においてRPAを活用すると、大きな効果が期待できます。


RPAブームの背景
RPAのブームには以下の時代背景があり、2020年のコロナ情勢により今後さらに拡大していくと考えます。
-
①生産年齢人口減少による人材不足
-
少子高齢化の進行により、日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、2060年には5,000万人を割り込むほどにまで減少すると見込まれています。
人材不足に伴って労働コストも上昇しており、これまで以上に仕事の生産性向上が求められている状況で、業務効率化につながるRPAに注目が集まりました。(出典)2015年まで:総務省「国勢調査」、「人口推計(各年10月1日現在)」、
2016年以降:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年4月)」(出生中位・死亡中位推計)
-
②AIブーム
-
昨今のAIブームにより自動化の気運が高まっている中で、RPAは導入しやすく効果も見えやすいことから急速に普及していきました。
RPAはAIを活用した事務高度化の第一歩と捉えられたのです。
-
③海外でのRPAの普及
-
特に欧米で2015年ごろからBPO事業者のRPA導入をきっかけに注目が高まり、全体の市場規模は約650兆円とも言われています。
この海外でのRPAブームの影響を受け、2016年ごろから日本でも注目されるようになりました。
RPAの強み
RPAの最大の強みはロボットの作業精度とロボットの安定性の高さです。
人間とは違い、長時間労働による集中力の低下もないため、生産性を最大限にまで高めることができます。
事務作業やルーティンワークが多ければ多いほど、 多人数で行っていた仕事をたった1台のRPAに任せることがメリットとなります。
-
「人件費がかからない」
-
人ではなくロボットが作業をしますので、退職・異動による人員の再配置・再教育も最低限のリソースで対応が可能になります。
繁忙期の一時的な定型業務のための採用の必要もありません。
そのため、採用コスト/人件費の削減が可能です。
-
「辞めない、働き続ける」
-
人間の労働時間は平均8時間×245日程度であるのに対し、ロボットは24時間×365日働き続けられます。
なおかつ大量のデータも素早く処理することができるため、大幅な効率化が見込めます。
-
「間違えない」
-
ロボットの作業精度は非常に高く、ミスがほとんど発生しません。
人間なら起こり得る集中力の低下によるミスの増加や生産性の低下も起きません。
見込まれる効果
RPA導入による最大の効果は人件費の削減です。
社員を単純作業から解放することで、自社への訴求力を向上させる効果もあり、働き方改革を推進するための基盤作りに最適です。
今後も、RPAを導入する企業はますます増えていくことが予想されます。
またRPAの導入によって、ルーチンワークや単純作業の多くがRPAロボットに置き換えられると、従業員はより人間力を必要とする仕事や、ロボットにはできない業務にシフトしていくことになるでしょう。
RPAを導入することで、業務内容が変わっていくのです。


RPAに適した業務
RPAツール導入で適した業務自動化の例を挙げると
- データ入力
- ファイルのアップロード
- 添付ファイルの保存
- 自動メール配信
- 文書ファイルのPDF化
- 定型文書のデータを登録・転記
- Web・業務アプリケーション間の受発注処理
- 顧客情報の照会
- システムからデータを抽出・集計
- 抽出データの加工
- 定型レポートの自動作成
- お問合せ対応など
この他にも考え方次第では様々な作業に対応可能です。現在のホワイトカラーの事務作業の多くがこの条件を満たしています。
RPA導入事例
弊社がご支援しました、RPAツール導入で業務の自動化に成功された事例は以下の通りです。
- 大手鉄道グループ会社様(未収金回収確認とメール通知の自動化)
- 大手通信会社様(AI-OCRと組み合わせた依頼書登録、領収書照合の自動化)
- 大手製薬メーカー様(カンファレンスの運用報告書作成の自動化)
- 大手自動車メーカー様(発注作業に伴う複数システムへの入力の自動化)
RPA導入の3STEP
RPA導入を考える際、大まかな流れは以下です。

- 「RPA導入が初めてで、何から取り組めばいいかわからない」
- 「どんな業務がRPA化できるのか判断できない」
という場合は、セミナーや研修を受講したり、RPAベンダーへのお問い合わせ・ご相談をおすすめいたします。
RPA導入をご検討中のお客さまへ
私たちはソフトバンクで培ったノウハウをもとに、様々な業界のお客様のRPA導入支援を行ってまいりました。
対象業務の検討、ツールの選定、開発、運用まで幅広くサポートいたします。
まずは一度、私たちにご相談ください。